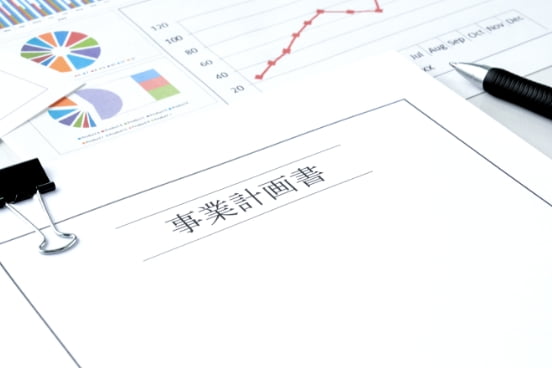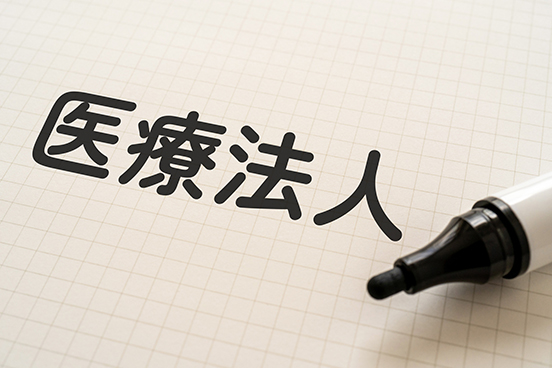クリニック開業の流れ・手順を徹底解説
更新日:
医院開業・医師開業・
クリニック開業専門コンサルタントが監修失敗しない医院開業手順

医院開業・クリニック開業を成功させるためのページです。開業を検討中の全てのドクターに不可欠な情報をまとめました。医院開業・クリニック開業に必要なことを確認しましょう。
この記事はDtoDコンシェルジュで医院の開業をサポートするコンサルタントが監修しています。 「開業を決意したものの、一体何から手をつけたらいいのだろう?」 これは開業を決めた医師が最初に直面する悩みだと思います。
また「開業準備に関する書籍などを通してやることがいろいろとあるのはわかったが、どう進めていけばいいのかよくわからない」という人もいらっしゃるのではないでしょうか。開業までの道のりは長く、そこにはさまざまな落とし穴もあります。 しかし開業に至るまでの行程はある程度決まっており、しっかりとした地図とコンパスがあれば、ほぼ確実に目的地へ着くことができます。
大事なのは最初に「いつ、何を、どのような段取りで進めていけばいいのか?」「各段階では、それぞれどんな落とし穴に気をつける必要があるのか?」の2つをしっかり確認しておくこと。
ここでは実例を交えながら以下の流れで医院開業までの流れについて紹介していきたいと思います。
目次
1. クリニックを開業するまでの流れ・スケジュール
医院を開業すると決めた後に、まず気になるのは「いつ頃から準備を始めるべきなのか?」でしょう。 新規開業の場合は少なくとも1年以上かけて準備するのが一般的です。多少の余裕を見込んで、開業希望時期の14ヶ月前頃から動くのが理想といえます。細かいスケジュールは開業形態や地域によって異なりますが、大まかには次のようなものになります。

このうち開業の予定が遅れる一番の原因となるのが、開業地の選定に時間をかけすぎることです。通常は上記のスケジュール通りに探し始めて3~4ヶ月以内には決まることが多いですが、
- 条件が厳しすぎてなかなかよい物件が見つからない
- 候補がたくさんあって決め切れない
などでなかなか決まらない場合、全体の進行に遅れが出ることは避けられません。
開業の時期については、特に有利な時期はないといえるでしょう。たとえば内科医院であれば「風邪やインフルエンザで患者さんが増え始める秋がいい」という話を聞きますが、開業当初は医師もスタッフも慣れないことだらけです。不十分な受け入れ態勢のまま多くの患者さんを迎えてしまい、そこでスムーズな対応ができなければ、結果として医院の印象が悪くなるというリスクも存在します。実際には、年度末で職場を退職し開業する医師が多いことから、4月や5月の開院が多くなっています。
2. クリニック開業までに必要な手順
クリニック開業までには、一般的に12のステップを経ることになります。開業をスムーズに行うには、あらかじめ各ステップで行う手続きやポイントを押さえることが重要です。この章では、クリニック開業の手順を具体的に解説します。
2-1. 経営理念・診療方針の策定
はじめに、「クリニックの開業目的・動機(経営理念)」と「自院が地域医療で目指すポジション(診療方針)」を策定します。理念や方針が明確になると、患者さんに対してクリニックが提供する価値も明確となり、集客やリピート施策が成功しやすくなります。
経営理念の策定では医師になった理由や医師自らの強みなどを、診療方針の策定では提供する医療サービスや役割を文面にします。
2-2. 開業地の選定・診療圏調査
次に、どこでクリニックを開業するかを決定します。大きく「都心×駅前」、「都心×住宅街」、「郊外×駅前」、「郊外×住宅街」という4つの選択肢があります。それぞれメリットとデメリットがあるため、予算や医師の強みなどに応じて検討します。
開業地が決定したら、診療圏(クリニック周辺)を調査します。主に、1院あたりの推計患者数や競合クリニックなどを分析します。現状のみならず、将来的な計画を含めた分析が重要です。
2-3. 不動産の選定・仲介
クリニックの物件を選定します。物件は、「戸建て」と「テナント物件」の2種類に大別でき、それぞれメリット・デメリットは異なります。経営理念や診療方針に基づいた物件選びが求められます。
特に、テナント物件の場合には、クリニック開業に適さない構造であったり、想定外の工事が必要となったりする可能性に注意が必要です。トラブルを避けるためにも、医療機関の専門知識を有する不動産仲介会社に相談するのがおすすめです。
2-4. 事業計画の策定
事業の成功のため、資金調達を有利に進めるために、事業計画を策定します。主に、経営戦略や目標をまとめた「経営基本計画」や、必要資金や自己資本比率、収支予想などをまとめた「資金・収支計画」を文章にまとめます。
資金・収支計画に関しては、売掛金回収までの期間を考慮し、費用を多めに見積もることが重要です。また、医師個人の支出も考慮して資金調達を図ることも求められます。
2-5. 資金調達支援
事業計画書の内容をもとに、開業や事業運営に必要な資金を調達します。自己資金と融資金額を把握しつつ、それぞれをどの費用に割り当てるかも決定します。融資の場合、金融機関によって返済期間や金利などの条件が異なるため、慎重に比較検討する必要があります。
クリニックの開業には多額の初期費用を要するため、円滑に調達を成功させるためにも、経験豊富なコンサルタントによる支援を受けるのがベストです。
2-6. 企画・設計・施工
住居や通常の店舗とクリニックでは、建築が大きく異なる点に注意が必要です。たとえば、清潔感やセキュリティ、法的な条件を満たすことなどが求められます。違いを踏まえずに設計や施工を開始すると、工程の後戻りや追加工事が必要となるおそれがあります。
施工着手後の軌道修正は難しいため、医療施設を担った実績が豊富な設計事務所や建築事務所の選定が不可欠です。
2-7. 医療機器選定・アドバイス
診療科目・方針に基づいて、必要となる医療機器を洗い出します。ただし、必要性を感じた医療機器を全て導入すると、資金不足に陥るおそれがあります。予算や調達計画をもとに、導入予定の医療機器に優先順位をつけることが求められます。
また、将来的に導入したい医療機器も併せて検討しましょう。この場合、稼働率や採算性などを踏まえて、合理的に導入可否を判断することが重要です。
採算性などをもとにした判断は難しいため、医療機器選定の知見や実績がある専門家からアドバイスを受けることがおすすめです。
2-8. リスクマネジメント
開業医は勤務医と異なり、自らがケガや病気で働けない期間が発生した場合、収入がなくなる上にクリニックに対する信頼が低下するリスクもあります。そのため、就業不能となる事態に備えて、所得補償の保険には最低限加入しましょう。
また、自然災害や火事、クレーム・トラブル、医療事故などに備えるための保険にも加入するとベストです。
2-9. 税理士・公認会計士の紹介
クリニックの経営では、会計帳簿や税務書類の作成が不可欠です。費用を抑えるために自力で行うことも可能ですが、莫大な労力や時間がかかり、本業に支障をきたすおそれがあります。
プロである税理士や公認会計士にサポートしてもらうことで、会計や税務の負担が軽減され、診療業務や経営に集中できます。また、開業後の事業計画や資金繰りに関するアドバイスも期待できます。
2-10. 職員の募集・採用・研修
クリニック経営に欠かせない看護師や受付、事務などのスタッフを採用します。
周辺地域やクリニックの専門領域をもとに、適した人材の募集が重要です。また、就業規則を明確化することで、スタッフとの間でトラブルになるリスクも軽減しましょう。
研修では、医療機器の使い方や診療シミュレーションだけでなく、患者との接し方や挨拶、言葉遣いなどの基本的なマナーを身につけてもらうこともポイントとなります。
2-11. 広報支援
集客や診療方針、院長の想いなどを伝えるために広報を行います。主な広報手段として、見学会やチラシの配布、Webサイトの運用などが挙げられます。
効果的な広報を行うには、各分野の専門家(広告代理店など)の支援を受ける必要があります。また、法規制に反さない内容での制作を要する点にも注意です。
「いつの間にか、よくわからないクリニックが開業していた」という印象を持たれないためにも、開業前から本格的な広報活動を実施することがポイントです。
2-12. 開業手続
クリニック開業に必要な届出や申請を実施します。たとえば、保健所には「診療所開設届」、厚生局には「保険医療機関指定申請書」などの書類を提出します。
開業する地域によって、提出する書類の種類やタイミングなどが異なる点に注意が必要です。提出時期を間違えると、開業を延期する事態となり得ます。コンサルタントなどのアドバイスをもとに、「いつ、どこに、何を提出するのか」を事前に整理しておくことが重要です。
3. 開業後によくあるトラブル

数々の難関をクリアして開業しても、それは「始まり」であって「ゴール」ではありません。お店や会社と同じように、5年、10年と続けていくことができて、初めて「開業成功」といえるでしょう。安定した医院経営のために、知っておくと役に立つ、開業後に起こりがちなトラブルとその原因についてもまとめて紹介します。失敗事例として確認しておきましょう。
3-1. 患者さんが少なくて不安になる
経営的に軌道に乗るまでには1~2年程度かかることが普通であり、最初は思ったより少ないのもよくあることです。 特に他の医院との違いを打ち出しにくい一般内科では、集客には時間がかかりがちです。 集客は1~2年のスパンで考え、その間は事業計画書通りに患者数が増えているかを確認し、増えていなければ対策を講じていく必要はありますが、概ね3年目で経営を軌道に乗せることを目標にしてみるといいでしょう。
3-2. スタッフ同士の諍い(いさかい)や人間関係のトラブル
スタッフ同士の揉め事や諍い(いさかい)は多くの医院で起こる、避けられないトラブルの筆頭格です。大したこともなく自然に解決する場合もありますが、最悪の場合はスタッフが次々に辞めてしまうことも起こり得ます。 日頃から院内の人間関係には目を配り、問題がありそうなら間に入って話を聞くなど、早めに対処していく必要があります。
3-3. スタッフとの労使関係トラブル
院長とスタッフの間でも「言った言わない」とか「指示を勘違いした」など、労使関係のトラブルは起こりがちです。対策としては、雇用条件や勤務規定など、法的なものは社会保険労務士に依頼してきちんと整理しておくこと。また、日頃から、スタッフとコミュニケーションをとっておくことが大切です。
3-4. システム面でのトラブル
患者さんが増えてきた頃によく出てくるのが、「待ち時間が長い」というクレームです。完全に解消することは難しいですが、待合室の改築や予約システムの導入、受付のアナウンスを変えるなどの方法で対応できる場合もあります。
このように、失敗事例としてまとめると開業後のトラブルの原因となるのは、ほぼ「お金」か「人間関係」のどちらかであることがわかります。
お金に関しては、
- 1日、1週間、1ヶ月、3ヶ月、半年、1年で来院数・診療単価の確認を行う
- 毎月の支払い額を確認し、資金がショートしないように気を配る
- 機器の過剰投資を避ける
- 「経費になるか否か」など、常に経営者の目線からお金を考える
の4つを実践していれば、だいたいのトラブルは防げます。また人間関係に関しては、「スタッフの雇用主である自覚を持ち、こまめにコミュニケーションをとる」ことで大きなトラブルに発展する前に対処できます。
4. クリニック開業を成功させるコツ
4-1. セミナーに参加して情報収集
1つ目は、セミナーへの参加です。ここまでお伝えしたとおり、クリニックの開業には、会計や法務、マーケティングなどの専門的な知識が必要です。また、法的要件を満たす建築の実施をはじめとして、通常のビジネスとは異なる対応も多いです。
以上の理由より、自力で開業を成功させる難易度は高いです。十分な知識を身につけずに開業に着手すると、想定外のトラブルによって開業が頓挫したり、開業後の経営に失敗したりするおそれがあります。こうした事態を防ぐためにも、クリニック開業に関するセミナーに参加し、必要な情報を学んでいくことが重要です。
弊社でも、医院の開業を目指す先生方を対象とした無料セミナーを開催しています。クリニック開業を成功させたい先生は、ぜひご参加ください。
4-2. 診療圏調査
クリニック開業における手続きの中でも、特に成功を左右するのが「診療圏調査」です。
競合となる周辺医院を調査することで、事前に推定患者数を洗い出し、成長戦略や収益計画を立てやすくなります。また、現時点における競合クリニックの強みや、将来的に競合となるクリニックが開業する可能性も分析できます。
調査が疎かになると、十分な患者数を確保できずに、クリニック開業が失敗となるリスクが高まります。こうした事態を防ぐためにも、診療圏の調査は不可欠です。
弊社では、無料で診療圏調査を承っています。Webからの申込みをいただくことで、1週間程度を目安に調査結果資料を作成・送付いたします。ぜひこちらもご利用を検討してみてください。
4-3. 開業支援会社の活用

医師の開業に関しては、工程の一部又は大部分を代行してくれる「開業支援会社」が存在しています。
開業支援会社の利用には、主に以下のメリットがあります。
- 労力を減らせる
- アドバイスをもらえる
- 開業後、軌道に乗るまでのケアを受けられる
サービス内容は会社により千差万別です。 おすすめなのは、取り扱い件数が多く、さまざまなノウハウを持っており、かつ長期的なサポートを行ってくれるところです。しっかりと準備を重ねて、自分ならではの医院開業を成功させましょう。
4,000件以上の開業実績を有する弊社では、開業予定の先生方に向けて、個別相談会を随時受け付けています。経験豊富なコンサルタントが、開業を成功させるポイントや手続きの詳細などの具体的な相談にお答えします。無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。